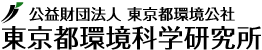高濃度光化学オキシダントの低減対策に関する研究(2022-2024年度)
令和7年度外部研究評価委員会 終了研究の事後評価
| 研究テーマ |
高濃度光化学オキシダントの低減対策に関する研究【終了】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和4~6年度 |
| 研究目的 | 光化学オキシダント(Ox)高濃度日を減少させるため、人為起源の中でOx生成への寄与が大きい揮発性有機化合物(VOC)成分や更なる対策が必要な発生源を特定するとともに、植物や大気中の二次生成によるOx生成への影響等を把握し、人為起源VOCによるOx生成への寄与割合の推定に資する調査研究を行う。 |
| 研究内容 |
|
| 事後評価 | A:優れている 5 B:普通 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|