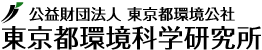都有施設のゼロエミッションビル化に向けた調査研究(2023-2025年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
都有施設のゼロエミッションビル化に向けた調査研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和5~7年度 |
| 研究目的 | 都有施設におけるエネルギー消費構造を詳細に調査した上で、消費構造に応じた対策を講じた場合に想定されるCO₂排出削減効果及び中長期的な電力消費量の変動を推計すると共に、脱炭素化の実現が困難とされる用途の特定・整理を目的とする。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 2 B:普通 3 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 3 B:普通 2 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|