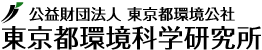有害化学物質によるリスク評価及びその危機管理に関する研究(2023-2025年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
有害化学物質によるリスク評価及びその危機管理に関する研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和5~7年度 |
| 研究目的 | 化学物質による環境リスクを低減していくためには、環境実態の把握及び排出源の解明が必要である。そこで、都内において環境影響を及ぼす可能性のある化学物質を選定し、環境実態調査を通じて排出源や環境リスクの解明を進め、ひいてはその削減に関する手法について提言を進める。さらに化学物質漏洩のリスクに備え、漏洩物質を早期に解明する分析技術を高めるとともに、都内の化学物質を取り扱う事業所の情報を把握し、その可視化を進めることで環境局の災害対策事業への活用に役立てる。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 5 B:普通 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|