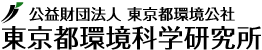熱分解GC/MSによるプラスチックの分析に関する研究(2023-2025年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
熱分解GC/MSによるプラスチックの分析に関する研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和5~7年度 |
| 研究目的 | 都が策定したプラスチック削減プログラムにおいて、廃プラスチック焼却量40%削減が 2030 年目標として掲げられている。リサイクルが困難とされる複合化(ブレンド、積層化など)された廃プラスチックに着目して、その成分分析や添加剤の使用について実態を調査し、廃プラスチックをリサイクル材料として利用する場合の課題などを整理し、都施策に寄与する情報提供を行う。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 3 B:普通 2 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 2 B:普通 3 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|