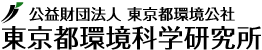使い捨てプラスチックの削減による環境負荷低減の検証に関する研究(2023-2025年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
使い捨てプラスチックの削減による環境負荷低減の検証に関する研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和5~7年度 |
| 研究目的 | 都が策定したプラスチック削減プログラムにおいて、廃プラスチック焼却量 40%削減が2030 年目標として掲げられている。使い捨てプラスチックの使用状況、廃棄実態の他、使用せざるをえない理由などを調査し、温室効果ガスなど環境負荷への影響を分析し、その削減効果を検証する。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 2 B:普通 3 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|