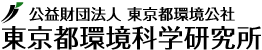都内河川における衛生指標細菌の発生源の推定に関する研究(2024-2026年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
都内河川における衛生指標細菌の発生源の推定に関する研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和6~8年度 |
| 研究目的 | 「『未来の東京』戦略」において、水と緑溢れる東京を実現する方策として、良好な水環境を更に高めていくことが提示されている(戦略13)。また、環境省は令和3年10月に生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を大腸菌数へ見直すとして、環境基準の改正について告示し、令和4年4月1日に施行した。都内の河川では下水道の普及等により水質が改善してきているが、衛生指標(大腸菌群数)は有機汚濁指標(BOD)ほど改善されていない。特に高い類型の河川を持つ区市の関心は高く、大腸菌が増大する要因を推定するための調査研究が必要となっている。そのため、代表的な都内河川を対象とし、大腸菌の発生源の推定に関して調査研究を行う。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|