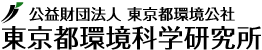水素エネルギーの実装化に向けた調査研究(2024-2026年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
水素エネルギーの実装化に向けた調査研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和6~8年度 |
| 研究目的 | 脱炭素化に向けた動きが加速する中で、水素エネルギーの位置づけがさらに重要視されている。グレー水素やブルー水素も含め水素エネルギーの実装化していくこととしているが、脱炭素社会に向けては再生可能エネルギー(再エネ)由来の水素(グリーン水素)の普及を進める必要がある。そこで、東京都内において利用する水素エネルギーについて、より温室効果ガスの排出が少ない水素にしていくために、都の地域特性や最新の技術開発動向を踏まえた低炭素水素の水準等を検証するための調査・研究を行う。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 5 B:普通 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 2 B:普通 3 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|