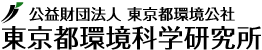保護上重要な野生生物種の保護策強化に向けた調査研究(2024-2026年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
保護上重要な野生生物種の保護策強化に向けた調査研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和6~8年度 |
| 研究目的 | 東京都生物多様性地域戦略(2023(令和5)年4月改正)に基づき、野生動植物保護に関する効果的な保護方策の検討や、東京の生物多様性の保全・回復に向けた施策を実践するためには、生態系及び種、遺伝子レベルでの生物情報や知見等に関する科学的根拠が不可欠である。そのため、都内における野生動植物相の把握や、保護上重要な生態系及び種の保全に資する調査研究を行い、生物多様性の回復に向けての検討を行う。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 5 B:普通 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 2 B:普通 3 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|