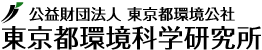微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究(2023-2025年度)
令和7年度外部研究評価委員会 継続研究の中間・事前評価
| 研究テーマ |
微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究【継続】
|
|---|---|
| 研究期間 | 令和5~7年度 |
| 研究目的 | PM2.5の高濃度化をもたらす二次生成物質について、ガス状前駆物質を含めて濃度変動特性を把握し、その発生源を明らかにすることを目的とする。また、ナノ粒子や大気中マイクロプラスチック等の新たな環境問題に関する情報を収集し、対策の必要性を検討する。 |
| 研究内容 |
|
| 中間評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|
| 事前評価 | A:優れている 4 B:普通 1 C:やや劣っている D:劣っている |
| 評価コメント及び対応 |
|